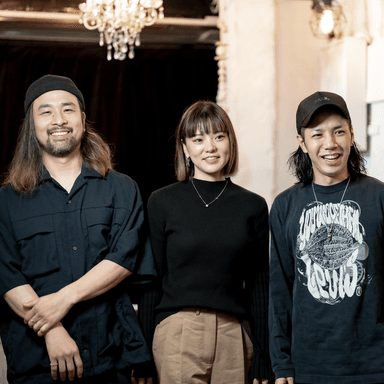電子音楽 × デジタルアート「MUTEK」アルゼンチン公演に招かれた日本人アーティスト Itti 〜オーディオビジュアルでの表現について
電子音楽とデジタルアートの祭典、MUTEK 。2000年にカナダ・モントリオールで初開催されて以来、スペインやチリなど世界各国で行われてきた国際的なイベントです。日本では2016年に “MUTEK.JP 2016” として初開催され、今年は記念すべき10周年を迎えます。そんな “MUTEK.JP 2025” の開催を 11月に控える中、10月にアルゼンチンのブエノスアイレスで行われた “MUTEK.AR 2025” に出演したアーティスト Itti 氏にインタビュー!MUTEK とは?オーディオビジュアルでの表現に行き着いた経緯とは?などをお伺いしました!
“MUTEK.AR 2025” 出演「デジタルと自然の境界を往復するような体験」
- “MUTEK” とは、どんなイベントですか?
MUTEK は、「MUSIC」と「TECHNOLOGY」という言葉から連想できるように、デジタル・クリエイティビティの発展と文化芸術活動の普及を目的とした団体です。
今回は Jotta.rs というアルゼンチンの映像アーティストとコラボして、オーディオビジュアルのスタイルで出演しました。
-オーディオビジュアルでのスタイルとは、どんなパフォーマンスですか?
音と映像が連動するライブパフォーマンスです。今回のパフォーマンスで言うと、僕が音を、Jotta.rs は映像を担当して、2人で1つの空間を作っています。
<MUTEK.AR 2025 Itti & Jotta.rsによるパフォーマンス>※音量注意
-アルゼンチンで開催された “MUTEK.AR 2025”( 以下、MUTEK.AR )に出演したきっかけを教えてください。
昨年、アルゼンチンのアーティストが日本に2〜3週間滞在して、現地のアーティストとコラボするレジデンス・プログラムがあり、それで Jotta.rs が来日していました。彼がコラボする相手を探していた時、Tomomi Horikawa さんという共通の友人が僕を紹介してくれて、それで一緒に日本でオーディオビジュアルパフォーマンスをしたんです。
その後も「また一緒にやりたいね」と彼と話しており、過去のパフォーマンスをプロジェクト化し、ドキュメントにまとめて MUTEK AR に送ったところ今回出演が決まりました。
-今回のパフォーマンスのテーマは?
Symbiotic Fractures(共生的断裂)です。映像も音も、例えば1秒ごとに規則的に変化し続けるものだと少しつまらないと思うんですけど、でもそれが1秒、0.8秒、0.6秒、0.9秒...のような感じで不規則になると、グルーヴが生まれるんです。これって風の音とか、鳥の鳴き声の強弱とかタイミングとかも多分同じなんじゃないかなって思っていて。不規則なんだけど不安定じゃないと言いますか。
映像にグリッチを加えたり、音にディストーションやディレイをかける行為には、自然が本来持つ不規則さや複雑さと共通する部分があると感じています。僕たちは、その “ゆらぎ” を意図的に取り入れることで、デジタルと自然の境界を往復するような体験をつくれないかと考えました。

-スクリーンに映し出された映像と、サウンド。まさに没入型のアートですね。今回のライブ・パフォーマンスはどのように構築されたんですか?
音と映像は基本的には同期させていたんですけど、お互い即興でパフォーマンスをしました。
僕はいつもライブ用に20曲ぐらい作って、それをキックとパーカッションとハイハットと、シンセと、FX と...みたいな感じで楽器のパートごとにバラバラにするんです。なので、素材自体は事前に作り込んであるんですけど、それらを即興で組み合わせていくスタイルでパフォーマンスします。
EQ やリバーブやディレイなどのエフェクトもその場でコントロールするので、曲はあるようでないといいますか、ライブ中に新しい曲が生まれる瞬間もよくあります。ミスがあったとしても、それが逆に良いアクセントになる時もあってやってて面白いんですよね。終わった後反省することも多いのですが(笑)
-その瞬間でしか生まれないものを感じながら、シームレスに曲が移行していく変化も楽しそうです。会場の雰囲気はどんな感じでしたか?
踊る人もいるんですけど、大体の人は揺れる程度で音楽と映像に集中している印象を受けます。MUTEK.JP にも出演したことがありますが、アルゼンチンは日本よりも比較的踊る人が多いなと感じましたね。日本だとオーディオビジュアルはアートを鑑賞する感覚に近いのかもしれないです。もちろん、楽しみ方は人それぞれなのでどちらも良いと思います。
-今回 MUTEK.AR にご出演されてどうでしたか?
シンプルに Jotta.rs と2人で一緒にやりきったことが一番嬉しかったですね。あと、今回 MUTEK.AR でプレイしたというのはもちろんなのですが、日本の真裏のアルゼンチンでプレイしたことも大きな自信になりました。ドラクエではぐれメタルを倒し、いきなりめっちゃ経験値を獲得した時の感覚と近いです(笑)。
-アルゼンチンはかなり遠いですよね。旅にも近い部分があったかと思いますが、一番印象に残っている出来事はありますか?
日本から30時間くらいかかりましたね。
印象に残っていることはたくさんあるんですけど...友達と家で飲みながらお互いの好きな曲をそれぞれ紹介し合ったのが面白かったです。僕は「ジャパニーズレジェンド」と言って井上陽水さんを紹介したんですけど、みんなハマってくれて。なんかバイブがいいと言ってましたね(笑)。音楽は言語が関係ないところが面白いですよね。
反対に、僕はアルゼンチンのロックを教えてもらいました。今まで聴いたことなかったんですけど、アルゼンチンでロックが隆盛した60〜70年代ごろは社会が不安定で、自由に言えないことが多かったそうなんです。だからこそ、“自分たちの言葉で歌うロック” が一気に広がったんだとか。その話も聞いたことで、友達をより理解できた気がして、すごく良い体験でした。

MUTEK との出会い「 ”表現ってこういうので良いんだ” と、自分の中で気づきがあったんです」
- MUTEK との出会いはいつ頃でしたか?
日本で初めて MUTEK を開催する際に、撮影のお仕事をさせてもらいまして、それが知ったきっかけです。MUTEK.JP が今年で10周年なので、ちょうど10年前くらいですね。なので、最初はアーティストではなく、撮影アシスタントとして現場に入ってました。
その時、出演アーティストである Herman Kolgen が自身の作品について解説をするトークセッションがあったのですが、撮影しながら聞いていたらそれがすごく響いちゃって。内容は「なんでこの作品を作ったか?」ということを解説していくものだったんですけど、それを聞いてたら「表現ってこういうので良いんだ」と、自分の中で気付きがあったんです。
(Itti さんのきっかけとなった Herman Kolgen の作品)
そこから自分の制作モチベーションがかなり上がって、MUTEK と出会ってなかったらどうなっていたんだろうというくらい、自分にとっては大きなきっかけとなりました。
ただ、その時はまだ僕は音楽家としては駆け出しだったので、出演は夢のまた夢という感じでした。
オーディオ・ビジュアルでの表現について「ここが居場所かも」

-オーディオ・ビジュアルに行き着いたきっかけは?
僕が初めて MUTEK のメインプログラムに参加した、2023年の “MUTEK.JP 2023” がきっかけです。
僕がやってる音楽は、ドラムンベースというジャンルが土台なんですが、サブジャンルがとても多いんです。その中でも、ハーフステップやエクスペリメンタルといったものに分類されると思います。これはクラブ・ミュージックの中でも結構ニッチなジャンルで、それまでクラブ・シーンの中で自分の音楽を表現する居場所はどこだろうと、悩んでいたんです。
映像と一緒に音楽をパフォーマンスしたことはなかったんですが、“MUTEK.JP 2023” で初めて映像アーティストの方や書道家の方と協力し空間演したことがとても楽しくて、「ここが居場所かも」と直感的に感じて、そこからオーディオビジュアルのスタイルを意識してやるようになりました。
- Itti さんが思う、電子音楽 × 映像で表現する良さは何ですか?
もちろん音だけでも成立するんですけど、映像が入ることで自分の世界観が立体的に開いていく感覚があって、そこがいいと思います。音が映像を動かし、映像がまた音の捉え方を変えてくれる、みたいな。
-実際のパフォーマンスの映像も拝見しましたが、モジュラーシンセを使っているのが印象的でした。こちらもこだわりなどあるのでしょうか。
以前は DAW 内だけで音楽を作っていました。DAW は画面を見ながら音作りをするので視覚も使って音を作るのに対し、モジュラー・シンセや、ドラム・マシンは感覚的に操作できるので、より音に集中できるなって思ったんです。
あと、ハード機材全般に言えるのですが、良い意味での予期せぬハプニングが起こりやすいんですよ。例えば、間違えて違うツマミをいじっちゃったけど、なんかかっこいい音になった!みたいな。そういうことが結構起こるのでモジュラーシンセをはじめハード機材を使うことにはこだわっています。
- Itti さんの今後の予定を教えて下さい
自分たちの会社が主催するイベント『ニッパチ祭』(※2)で、国内外で活躍している同世代の Dayzero というアーティストとのプロジェクトを初披露します。
このプロジェクトでは、クラブ・ミュージックの文脈からオーディオビジュアルセットに挑戦していく予定です。まだ本当に走り始めたばかりでユニット名も決まっていないんですけど、最初から世界を目指して活動すると決めています。海外レーベルからリリースはできると思っているんですけど、フェスやイベントに呼ばれるようになるとなると、ハードルがまた一つ上がるので、地道に頑張りたいですね。
(※2)12月6日(土)大阪の梅田の文化施設「VS.」で開催される、Itti さんが所属する会社主催のイベント。

-パフォーマンスが待ち遠しいです。ちなみに映像アーティストは?
何でも自分でやってみたくなっちゃう性格なので、実は映像にも挑戦中なんです(笑)。なので、このプロジェクトの映像担当は自分がメインだと思います。とはいえ、まだどうなるかわかんないですけどね。活動して最初の方は映像アーティストをゲストで呼ぶかもしれないですし、まだ色々と試行錯誤中です。
ちなみに『ニッパチ祭』では、Atsushi Kobayashi さんというアーティストが映像を担当してくれます。
-楽しみにしています。Itti さんの個人的な目標はありますか?
抽象的な表現になってしまうんですけど、日本人の精神性や美意識を、音を軸にして探求したいです。現代の音楽理論・作曲法の多くは西洋を基盤としていて、日本独自の感性や価値観が十分に注目されてこなかったと思っています。しかし、そこにはまだ掘り起こされていない魅力や可能性が眠っているはずだと直感で感じています。
まとめ
国内外で活躍する Itti 氏。インタビューを通して、「音」に対する向き合い方が印象的でした。
「即興」で音を楽しみながらのパフォーマンスや、モジュラーシンセで音に集中する制作の過程からも、「音」そのものを大切にしている姿勢が伝わってきます。
居場所を探していることもあったという時期も経て、自分の好きな音と向き合いながら導かれたオーディオビジュアルの世界。繊細に音と向き合うことで、Itti 氏ならではのパフォーマンスが生まれているのだと感じました。
電子音楽を日頃から楽しんでいる方も多いと思いますが、映像と融合したその「空間」を体験することで、また新たな世界への扉が開かれるかもしれません。今回 Itti 氏が参加した MUTEK.AR の日本公演 MUTEK.JP は、11月20〜23日に渋谷で開催されます。音、そしてアートで楽しむデジタル・クリエイティブの祭典。是非足を運んでみてはいかがでしょうか。
◾️MUTEK.JP 2025 Edition 10

日程:11月20(木)〜 23日(日)
会場:
SpotifyO-EAST
WWW
MIYASHITAPARK「or」
渋谷ヒカリエホール
渋谷スクランブル交差点

Itti 氏プロフィール
世界6カ国13レーベルから48曲をリリースし、アルゼンチンをはじめ、ベルギーやクロアチアなど世界各地のイベントでパフォーマンスを行っている。過去には、ドラムンベースシーンのレジェンド dBridge とも楽曲を共作。
12月6日(土)には、自身が主催する『ニッパチ祭』を大阪「VS.」で開催予定。
ニッパチ祭 Webサイト
Itti 氏へのご依頼はこちらから可能です。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。