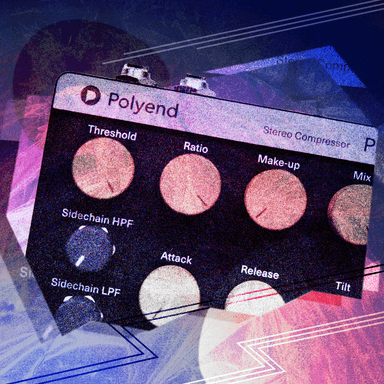〜 目次 〜
- 1音程(インターバル)とは
- 2音程とピッチの違い
- 3音程の単位
- 4音程の種類を全てご紹介!
- 4.1完全1度(Perfect Unison)
- 4.2短2度(Minor Second)
- 4.3長2度(Major Second)
- 4.4短3度 (Minor Third)
- 4.5長3度(Major Third)
- 4.6完全4度(Perfect Fourth)
- 4.7増4度 / 減5度(Augmented Fourth / Diminished Fifth)
- 4.8完全5度(Perfect Fifth)
- 4.9短6度(Minor Sixth)
- 4.10長6度(Major Sixth)
- 4.11短7度(Minor Seventh)
- 4.12長7度(Major Seventh)
- 4.13完全8度(Perfect Octave)
- 5音程の頭につく、「完全」、「短」、「長」、「増」「減」...って何?
- 6音程が分からない方へ
- 7番外編:単音程と複音程
- 8まとめ
音程(インターバル)とは
音程とは、音と音との距離のことです。英語で interval(インターバル)とも呼び、和訳すると「間隔」という意味になります。
イメージとしては、距離をイメージすると良いでしょう。
地点A を基準とした場合、地点A から地点B までの距離、地点A から地点C までの音の長さ...音程もこのようなイメージと同じです。
つまり、音程は音が2つ以上存在しないと測れないものです。
音程は面白いことに、2つの音の距離が変わるだけで、音の響きが変わります。
例えば、ドとミはどことなく安心する印象です。一方でドとファ#では、どこか不安になる印象です。

音程は「和声的音程」と「旋律的音程」の2種類があります。和声的音程とは、2つの音を同時に鳴らした時の音程です。一方、旋律的音程とは、2つの音を個別に連続で鳴らした時の音程となります。
音程とピッチの違い
音程を正しく理解するために、まず押さえておきたいのが「ピッチ」との違いです。
ピッチとは、単体の音の「高さ」そのものを表す言葉です。たとえば、楽器のチューニングでよく使われる「ラ」の音は、一般的には440Hz(ヘルツ)という数値に設定されています。
この「Hz(ヘルツ)」という単位は、1秒間に空気が何回振動しているかを示していて、振動数が多いほど高い音、少ないほど低い音になります。つまり、ピッチは一つの音だけで決まる絶対的な高さなのです。
一方で、音程は、二つの音の「距離」を表します。これは相対的な関係であり、どちらかの音を基準にして、もう一方の音がどれくらい離れているかを測っています。
音程の単位
音程を表す単位は、「度(degree)」で表します。
次章で数え方を詳しく解説していきます。
音程の種類を全てご紹介!
この章では、音程の種類を詳しくご紹介します。
ピアノの鍵盤を眺めてみると、音は12種類しかありません。そのため音程も12種類となります。
それぞれの音程の響きを聴いて、違いを感じましょう。
※()は英語名の略称
完全1度(Perfect Unison)
半音:0個分
英語略称:P1

短2度(Minor Second)
半音:1個分
英語略称:m2

長2度(Major Second)
半音:2個分
英語略称:M2

短3度 (Minor Third)
半音:3個分
英語略称:m3

長3度(Major Third)
半音:4個分
英語略称:M3

完全4度(Perfect Fourth)
半音:5個分
英語略称:P4

増4度 / 減5度(Augmented Fourth / Diminished Fifth)
半音:6個分
英語略称:A4/d5

完全5度(Perfect Fifth)
半音:7個分
英語略称:P5

短6度(Minor Sixth)
半音:8個分
英語略称:m6

長6度(Major Sixth)
半音:9個分
英語略称:M6

短7度(Minor Seventh)
半音:10個分
英語略称:m7

長7度(Major Seventh)
半音:11個分
英語略称:M7

完全8度(Perfect Octave)
半音:12個分
英語略称:M8

音程の頭につく、「完全」、「短」、「長」、「増」「減」...って何?
これまで音程の説明を見ると、完全○度、短○度、長○度など、様々な名前があります。
これらの違いは、音程の特性によるもので、英語で「Quality(質)」といいます。
それぞれ聴覚特性が異なります。
ちなみに完全「1」度などの数字の部分は、クオンティティといいます。
完全
完全音程は、1、4、5、8度があります。
短、長
短長の音程は2、3、6、7度があります。
増、減
増減の音程は、増4度、減5度があります。
音程が分からない方へ
「音程が分からない」「メロディーが取れない」とお悩みの方もいると思います。
ただ、それは、音と音の距離感がまだ感覚として身についていないだけなのです。
それぞれの音程の響きを少しずつ覚えていくことで、自然と音程が取れるようになってきます。
例えば「ド → ミ」のように、「ドレミファソラシド」の音階を使って、実際に声に出して歌ってみるのは効果的です。
また、有名な曲の出だしを分析して、それを音程の目印にするのもおすすめです。
たとえば、童謡「きらきら星」の出だしは「ドドソソ」。音程で言うと「完全一度 → 完全五度」となります。
このように、他の曲でも同じような音の間隔(=音程)を見つけて繰り返し歌うことで、音程感覚は徐々に身についていくでしょう。
番外編:単音程と複音程
今回は、12個の音程についてご紹介しましたが、実は12個以上離れた音程を表す言葉もあります。
単音程
単音程とは、完全1度から完全8度までの音程のことです。
複音程
複音程は、完全8度を超えた音程のことです。
複音程では1オクターブ上離れた完全1度から完全8度までの音程に置き換えて考えることができます。
例えば、12度は1オクターブ上と完全に4度離れた距離となります。
まとめ
以上、今回は音程(インターバル)についてご紹介しました。
音程をしっかり理解することは、コードやスケールなど、より複雑な音楽理論の習得にも大きく役立ちます。ぜひ、実際の音を聴きながら、音程感覚を養っていきましょう!

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。