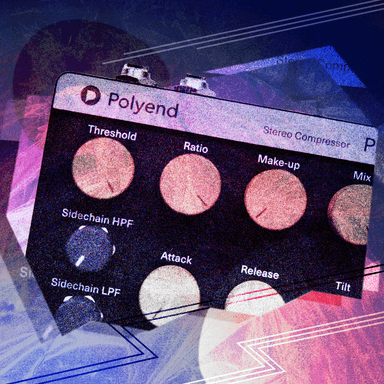南北戦争後〜マーチングバンド的ドラム(1800年代中盤)
打楽器自体は、はるか昔から存在していましたが、現代のドラムは軍楽隊で基盤が作られたと言えるでしょう。
「軍楽隊」とは、軍隊で楽器演奏を担う人々のことで、彼らは軍人の士気を高めるために楽器を演奏したり、号令や合図、通信手段として、楽器を演奏していました。
1861年から南部と北部の対立によって勃発したアメリカの内戦「南北戦争」でも、この軍楽隊が編成されました。1865年に南軍が降伏した形でこの戦争が終わりを迎えると、軍楽隊が解散され使われなくなった楽器が安価な値段で市場に出回るようになります。
これにより、楽器を手にした南部のアフリカ系の人々たちは(※)、街でマーチングバンドやブラスバンドを組み、演奏を楽しみました。
この時はまだ、ドラムセットというものはなく、スネア、バスドラム、シンバルなど、1つの楽器につき1人の演奏者。ドラムの演奏も「ルーディメンツ」といって、軍の時に使用されていた叩き方を採用していました。ちなみに、このルーディメンツは、現代でもドラム練習の基礎として知られています。
また、リズムは主に1拍目と3拍目にアクセントがあるもので、これはマーチ(行進曲)に由来していました。
(※奴隷制度時代、アフリカに住んでいた人々は、労働力としてアメリカの南部へと連れてこられました。その影響で、1865年に奴隷制度が廃止してもなお、南部にアフリカ系の人々人口が集中していました)
複数の楽器を1人の演奏者が演奏(1800年代後半)
ブラスバンドやマーチングバンドは人気になっていき、次第に劇場や舞台での演奏需要が高まりました。しかし、予算の関係で、打楽器演奏者たちは1人で複数の楽器を演奏することが求められ始めます。
現在では、バスドラムにはキックペダルがありますが、この頃はまだ発明されておらず、バスドラムとスネアをスティックで交互に演奏する「ダブルドラミング」という奏法が生み出されました。
こうして、複数の打楽器を1人で演奏するようになっていきます。
1800年代後半になると「ラグタイム」という音楽ジャンルが発展。
ラグタイムはピアノで演奏され、マーチングバンドのリズムに「シンコペーション」や「スウィング」などといったアフリカ系アメリカ人特有のリズムが合わさった音楽です。
この独特なリズムは、人々を踊らせる力を持ち、人気のリズムとなっていきました。
ジャズとドラムセット(1900年代初頭)
1900年代初頭、アメリカ南部のニューオリンズでは、マーチングバンドやブラスバンドが、ラグタイムのシンコペーションや、スウィング、またフィルインを取り入れるようになりました。
こうして初期のジャズ「ニューオリンズジャズ」が形成されました。
当時のアメリカにはアジア、ヨーロッパ、中東から移民が増えたことに伴い、各地の民族楽器も流入しており、バスドラム、スネアに加え、これらの民族楽器も取り入れていたとされています。
民族楽器由来の様々な小物打楽器も演奏することから当時はこのような打楽器演奏者は「トラップ・ドラマー」と呼ばれていました。このトラップは、英語で「装置」という意味を持つ contraption の略称だと考えられます。
また、この頃にはキックペダルも販売され、ダブルドラミングで演奏されていたバスドラムは、ペダルによって演奏されるようになりました。
当時の主なドラムセットは、バスドラム、スネア、ウッドブロック、中国の太鼓、シンバルなど。写真からも分かる通り、ハイハットはまだありませんでした。

シカゴジャズからビッグバンドジャズ(1920年~1930年代)
1920年代、アメリカでは禁酒法が施行されました。
この禁酒法により、アメリカ全土でアルコールが禁止されたことで、違法でお酒が飲める「スピークイージー」と呼ばれる、もぐりの酒場が人気になりました。このスピークイージーでジャズが演奏され、ジャズはシカゴで更なる人気を獲得します。
このように、禁酒法時代に流行したジャズを「シカゴジャズ」と言います。
当時の演奏家たちは、ジャズバンドだけでなく、ラジオやショー、無声映画でも活躍。ラジオでは、BGM として番組を盛り上げたり、無声映画では伴奏、そしてドラマーは効果音も担当していました。
このような流れを受け、1930年代に入ると酒場で演奏されていた即興的な「シカゴジャズ」から、より大規模な編成で楽譜に基づいて緻密に構成された「ビッグバンド・ジャズ(スウィング・ジャズ)」へと発展していきます。
このビッグバンド・スタイルでは、演奏が決められた時間内で効率的に演奏することが求められるようになりました。
リズム面でも大きな変化がありました。
シカゴジャズまでのリズムは、マーチ音楽に影響を受けた「ドン、タン、ドン、タン」といったツーフィール(2ビート)で演奏されることが主でしたが、ビッグバンド時代には「ドンドンドンドン」と4拍すべてにアクセントを持つフォーフィール(4ビート)へと移行し、よりダンス音楽としての性格を強めていったのです。
また、これまでにもハイハットの前身となるものはみられましたが、1930年代付近に現代の形のハイハットが確立されていきました。
シカゴジャズ
ビッグバンドジャズ
<ドラマーのスター性〜 Gene Krupa>
当時の重要なドラマーとして欠かせない人物が、Gene Krupa(ジーン・クルーパー)です。
彼は、これまであまり華がなかったドラマーにスター性を持たせ、社会的地位を高めた人物です。
彼の演奏を見てみると、演奏にエンターテイメント性があり、そのハンサムな見た目も相まって、ドラマーも主役級の演奏者として地位を確立しました。
ビバップジャズで複雑化(1940年代)
これまでのダンス音楽とは一転、1940年代にはビバップジャズといって、芸術性や即興性が高いジャズが生まれます。
このビバップジャズでは、よりドラムは即興的で複雑なものとなりました。
より柔軟に演奏するために、バスドラムやスネアを小さいものへ変更したり、ライドシンバルを導入したりなど、ビックバンド時代から更なる変化もみられました。
リズム&ブルース〜バックビートの普及(1940年代後半)
1940年代後半になると、リズム&ブルース がダンスミュージックとして人気になりました。
リズム&ブルースについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
またリズム&ブルースの影響もあり、2拍4拍を強調した「バックビート」が演奏されるようになり、よりヘビーなドラムへと進化していきました。
ロックンロール〜スウィングからストレートに(1950年代)
リズム&ブルースやカントリーミュージックに影響を受け、1950年代にはロックンロールが普及し始めます。
ロックンロールの変遷を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
このロックンロールは、白人のティーンをターゲットに売り出されました。
また、第二次世界大戦の後ということもありエネルギッシュなサウンドをもっていました。
そのため、これまでジャズでは4拍目にクラッシュシンバルを鳴らしていましたが、ロックンロールでは1拍目に鳴らすようになり、スウィングしていたリズムはストレートになっていき、現代のロックサウンドの基盤がつくられます。
スウィングとストレートの違いはこちらの記事をご覧ください。
また、これまでドラムは他の楽器よりも大きな音量なため、他の楽器をかき消さないために工夫がされていましたが、1950年代ではエレキギターやエレキベースといった電子楽器が普及し始めたことにより、ドラムも派手で大きなサウンドを奏でることが可能になりました。
ビートルズの多大なる影響(1960年代)
当時アメリカで爆発的人気を誇っていた The Beatles は若者のロールモデルでした。
1960年代まで、ドラムの演奏スタイルは、トラディショナルグリップ(レギュラーグリップ)というスティックの握り方が主流でした。これは、もともとマーチングバンドのスネアドラムが体の前で斜めに吊られていたため、自然と左手が下から持ち上げるような構えになったことに由来します。
これを変えたのが The Beatles(ビートルズ)の Ringo Starr(リンゴ・スター)です。
ドラマーであるリンゴ・スターは、マッチドグリップというスティックの握り方で、影響を受けた若い世代のドラマーたちはこぞって真似しました。
こうして、マッチドグリップが自然と「標準の持ち方」へと定着していったのです。
さらに、彼が使用していた Ludwig(ラディック)社のドラムセットにも注目が集まり、ビートルズマニアの若者たちは「リンゴ・スターのようになりたい」と、Ludwigのドラムをこぞって購入しました。こうして、Ludwig社は一躍アメリカで最も人気のあるドラムメーカーとなりました。
まとめ
以上、今回はドラムの歴史についてご紹介をしました。
ドラムの形成は南北戦争、禁酒法、移民の流入などといったアメリカの歴史、ポピュラー音楽と密接な関わりがあることがわかりました。
歴史を知ることで、より楽器への理解だけでなく、同時にジャンルへの理解も深まるのではないでしょうか。
また、今回は一部しか触れられませんでしたが、ジーン・クルーパーやリンゴ・スターといった、これまでのドラムの概念を書き換えるようなスターが現れたことも、注目したい点です。音楽の歴史にはドラムだけではなく、これまでの概念を打ち破るミュージシャンがいて、それにより新たなジャンルやカルチャーが生まれたりします。スターの影響力に驚かされますね。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。