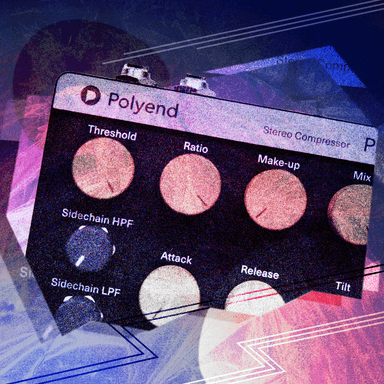音楽制作で活用できる AIツールをご紹介!〜楽曲制作初心者の方へのおすすめ〜
近年、AI(人工知能)の進化は目覚ましく、AI を活用した様々なツールが登場しています。 「これから楽曲制作を始めてみたい」「オリジナル曲をつくってみたい」と考えている方にとって、AIツールは音楽制作へのハードルを下げる心強い足がかりとなるでしょう。 この記事では、これから音楽制作に挑戦してみたいと考えている方や、趣味としてオリジナル曲づくりに興味のある方、すでに楽曲制作に取り組んでいるものの、まだ作り方がよく分からないという初心者の方々に向けて、音楽制作で活用できる AIツールと、その活用方法についてご紹介します。

 制作応援キャンペーン開催中!
制作応援キャンペーン開催中!AI とは?
AI とは、Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)の略称で、人工知能のことで、簡単にまとめると人間の知能で行われていることをコンピューターで行えるようにした技術です。
機械学習により、大量のデータをコンピューターが自ら解析し、学んでいくことが可能です。
楽曲制作においても進化する AI
ここ数年で加速度的に成長を遂げている AI業界。
AI を活用したチャット形式のサービスである「Chat GPT」 は利用者も多く、プライベートでも仕事でもかかせないツールとなっている方も多いのではないでしょうか。
音楽業界もその例に漏れず、現在音楽制作で活用できる様々な AIツールが開発されています。
最近では、 AI によって生成された楽曲を配信する『The Velvet Sundown』という AIバンド が、わずか数週間というスピードで月間100万回再生を突破したとして話題になりました。
当初 The Velvet Sundown の中の人は、AI で生成した楽曲だと公表はしておらず、AI 生成による疑惑を否定していましたが、ジャケット写真やサウンドから「AI で作られた音楽なのでは?」と物議を醸していました。
現在は AI で生成した音楽と認め、Spotify上の詳細情報欄に、作曲、ボーカル、ビジュアルは全て AI によって生成されていると明記されています。
このニュースからも、AI によって作られた音楽が、私たちの身近な存在になってきていることが分かります。
楽曲制作で活用できる AIツールをご紹介
この章では、楽曲制作で活用できる AIツールをご紹介します。
※Scaler 3は、DAW をお持ちの方のみご使用いただけます。
作詞・作曲で使える AIツール
Chat GPT
Chat GPT とは、対話型の AIチャットボットです。
質問した内容に対して、チャット感覚で回答してくれます。
このサービスは、作詞〜作曲のアイディア、またプロジェクトの進行まで、幅広く活用することができます。
たとえば、「メロディと歌詞はあるけど、この先楽曲を配信するには何をすれば良い?」などを質問してみると、その後の道筋を教えてくれるでしょう。
イメージとしては、音楽の先輩に質問をする...みたいなイメージに近いかもしれません。
Suno AI Music
Suno AI は、作詞、作曲だけではなく、ボーカル生成まで、まるっと楽曲を生成してくれる楽曲 AIサービスです。
楽曲のジャンルや雰囲気、テーマなどをテキスト入力することができ、数分で楽曲を生成してくれます。
歌詞を入力したらその歌詞に合わせて楽曲を生成することも可能です。
日本語、英語だけではなく、韓国語やスペイン語など、様々な言語に対応しています。

編曲で使える AIツール
Scaler 3
Scaler 3 は、正確には AIツールではありませんが、コード進行を生成する際に活躍するサービスです。
入力したメロディーのキーを解析し、そのキーで使用できるコードを教えてくれて、パズルのように感覚的にコード進行を作ることができます。
「メロディーは思い浮かぶけど、それをどう形にしていけば良いか分からない」という方におすすめです。

AIVA
AIVA は、自動で音楽を生成してくれる AIツールです。
サービス上で生成した楽曲の調整ができたり、MIDI出力も可能です。
AIVA で生成したアイディアをベースに、気になるところや、オリジナル性を出したいところは自分で手を加えることが可能です。

AI 機能を活用したDAW
近年では、AI 機能を導入した DAW も登場しています。たとえば、Apple社が提供する DAWソフト「Logic Pro」には、AIを活用した「Session Player」と「Stem Splitter」という機能が搭載されています。
「Session Player」は指定したコードやメロディーから自動で伴奏を生成してくれる機能です。一方、「Stem Splitter」は読み込んだオーディオをパートごとに分離できる機能で、こちらはリミックス制作や耳コピの際に便利です。
また、Image-Line Software社の FL Studio 2025 には、AIチャット機能「Gopher」が搭載されており、チャット形式で操作方法や楽曲制作について相談しながら進めることができます。
このように、DAW に組み込まれる AI 機能をサポートとして活用してみるのも良いでしょう。
楽曲制作で AI を活用する場合のメリット・デメリット
メリット
- 音楽知識がなくても制作できる
- 1人で始められる
- 多言語に対応している
- 自分では思いつかなかったアイディアを得られる
- 効率的で時短につながる
- 機材がなくても始められる
AI を活用した音楽制作の大きなメリットは、音楽に関する知識がなくても、プロンプト(※)で楽曲の方向性を指示することで、自分のイメージに近い曲を生成してくれる点にあります。
また、音楽制作に必要な機材をすべて揃えるにはコストがかかりますが、AI を使えば、低コストかつ1人で始められるため、最初の一歩を踏み出しやすくなるでしょう。
他にも、ジャンルや言語に対応したものや、特定の分野に特化した AI技術を使ったサービスも登場しています。さらに、効率的にアイディアを提供してくれることから、プロの制作者でも部分的に AI を活用している人は少なくありません。
(※)AIに指示をする文章
デメリット
- オリジナリティが薄まる
- 「創る」過程が楽しめない
- 著作権・倫理的な問題がある
- クオリティを求めるならプロの力が必要
- 必ずしも正しい情報とは限らない
- AI による生成を明記しなければならない場合がある
「とにかく曲数を量産したい」「雰囲気の良い音楽を手軽に作りたい」といったニーズを持つ方には、AI をフル活用した制作スタイルが向いているかもしれません。
一方で、オリジナル性を追求したい方、作る過程を楽しんでいる方、高いクオリティを求めている方には、すべてを AI でまかなう楽曲制作はおすすめできません。
なぜなら、Suno などの楽曲生成AI は、膨大な既存楽曲から学習することで、そのジャンルのスタイルや音色の傾向を模倣して楽曲を生成しており、ジャンルや雰囲気を指定すれば、そのスタイルを表現した曲が短時間で出力される一方で、過去の曲に似た印象になる可能性あり、個性が出しにくいといった側面があるからです。
ジャンルやプロンプトの指示によってはクオリティが高く人間が作った楽曲と見分けがつかないものもあります。しかし、指定したスタイルを表現できていなかったり、楽曲のサウンドが持つ迫力や表現力、細かいニュアンスに関しては、まだ人間のプロクオリティには及ばないことが多いです。
おすすめの活用方法
現時点では、AIツールは楽曲制作の補助的な活用方法が最もおすすめです。
楽曲の方向性を決める
「どんな曲の方向性にしよう?」と悩んでいる方は、まず曲の方向性から相談してみるのがおすすめです。
たとえば、歌詞は用意しているものの、どのような楽曲に仕上げるか迷っている場合でも、ChatGPT や Gemini などのサービスを使えば、一緒に楽曲の方向性を固めていけます。

効率的なアイディア出しに使う
AIツールは短時間でアイディアを生成してくれます。
たとえば、楽曲の方向性を固めるために楽曲生成AI を使って複数のパターンを出したり、特定ジャンルのコード進行のアイディアをいくつか生成したりすることなどが可能です。
自分が苦手分野の部分の補佐に使用する
自分が苦手とする分野に関して、部分的に AIツールを活用することもおすすめです。
例えば、自分の作ったメロディーにコード進行をつけたい場合、もしくはコード進行はあるけど「もっとおしゃれにしたい」などのお悩みにも、AIツールは活用できます。
また、作曲、アレンジまではなんとなく形になるけど、ミックスやマスタリングが分からない...という方にも、それぞれに特化したツールが存在します。
AI を叩き台にプロの手によってブラッシュアップ
楽曲制作を外注しようとお考えの方の中には、依頼する際にどのようにイメージを伝えるか悩んでいる方も多いと思います。
そんな時は、Suno などの楽曲生成ツールを使って「こんな楽曲にしたい」というイメージを具体化し、プロフェッショナルへ共有するという方法もあります。
さらに、そのアイディアをたたき台として、プロの手で楽曲を形にしていったり、よりブラッシュアップしていくのも良いでしょう。
ONLIVE Studio は、様々な音楽のプロフェッショナルが登録されており、楽曲制作を依頼したい人とプロフェッショナルを繋げるプラットフォームです。
ぜひご活用ください。
AI で楽曲生成をする場合の注意点
AI は大量のデータをもとに学習して楽曲を生成しているため、Suno などの楽曲生成AI サービスに対し、アメリカの大手レコード会社は2024年に AI の学習に無断で楽曲を使用したとして提訴しました。
現在 AI 関連の法整備が現在まだ整っていないため、このようなことも理解して使用する必要があります。
また、AI サービスを利用して生成した楽曲は、利用するサービスごとに規約が異なるため、AI を使って制作した楽曲を公開・配信する際には、必ず事前に利用規約を確認しておくことが重要です。
サービスやプランによって著作権の扱いなどが変わってくるため、この辺りも確認しておく必要があります。
まとめ
以上、今回は楽曲制作初心者向けに、活用できる AIツールをご紹介しました。
今回ご紹介したものだけではなく、AI を活用したツールはたくさん存在します。
楽曲制作初心者の方こそ、ご自身のニーズに合う AIツールを試して、楽曲作りのハードルを下げると良いでしょう。
今回は楽曲制作初心者の方へのおすすめツールをご紹介しましたが、楽曲はある程度できた!という方には、iZotope社が提供する、AIミキシングプラグイン「Neutron 5」や、AI マスタリングプラグイン「Ozone12」などもおすすめです。
これらのプラグインに自分の曲を読み込ませることで、曲を解析し、ミックスやマスタリングにおいて適切な調整を提案してくれます。
作曲ができたら、これらのプラグインを試してみるのも良いでしょう。
また、AI で物足りなく感じたら、プロフェッショナルに依頼してみるのも一つの手です。
音楽制作でお困りの方は、ぜひ ONLIVE Studio をご活用してみてください。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。