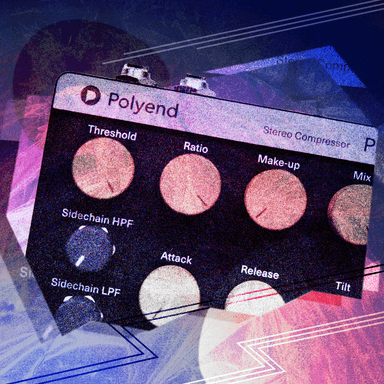(本記事に挿入されているギター写真はそれぞれのイメージです。文中の年代のモデルとは関係ありません)
音量の大きいものを求めて
1920年代、アメリカではビッグバンドジャズが流行しはじめました。ビッグバンドジャズとはその名の通り、大編成で演奏されるジャズのことです。
大編成のバンドの中では、楽器の構造に依存した音量しか出せない従来のアコースティックギターでは音が埋もれてしまいました。
そのため、より大きなギターの音量を求める需要が高まり、エレキギターの開発に向けた取り組みが活発になっていったのです。
1930年代に入ると、テキサスのギタリスト George Beauchamp(ジョージ・ボーチャム)が、弦の振動を電気信号に変換して増幅する「ピックアップ」を考案し、エレキギターの原型を生み出しました。さらに、彼と共同で Rickenbacker (リッケンバッカー)社が「フライ・パン(Frying Pan)」という商品名で商用販売を開始しました。このモデルは、エレキギターの先駆けとなった楽器です。
ただし、このギターは「スティール・ラップギター」という位置付けで、膝の上に載せて演奏するものであり、まだ現代でイメージされるエレキギターとはまだ異なる形をしていました。
ホロウボディのエレキ化
「フライ・パン(Frying Pan)」が登場した後、その技術を伝統的なスパニッシュギターに応用する試みが行われました。
1930年代中頃には、Gibson(ギブソン)社から「ES-150」が発売され、これは商業的に初めて成功を収めたエレキギターとされています。
ただし、このギターは「ホロウボディ」と呼ばれる中が空洞の構造を持っていたため、ハウリングが発生しやすいという特徴があり、実用化されてもなお課題も多く残されていました。
音響をより良く!ソリッドギターへの試み
1950年 Fender社 Esquire(Telecaster)
より良いサウンドを実現するため、「ソリッドボディ」によるエレキギターの開発が技術者たちによって進められました。
ソリッドボディとは、空洞を持たないボディのことです。
1950年代には、Fender(フェンダー)社が Esquire(エスクワイヤ) を発売。このモデルは、実用的に普及した最初のソリッドボディ・エレキギターの一つとされています。
発表当時はこれまでのホロウボディと違うその見た目から「雪かき用のスコップのようだ」と揶揄されたと、公式HP に記されていますが、結果的にこのギターは歴史に名を刻む存在となりました。
Esquire には発売当初、ピックアップが1基のモデルと2基のモデルが存在しており、その後、1基のものは Esquire、2基のものは Broadcaster(ブロードキャスター) と名付けられました。
しかし、この「Broadcaster」という名前は当時 Gretsch(グレッチ)社が販売していたドラムの商品名と重なっていたため、1951年に改名され、現在の Telecaster(テレキャスター) という名称が誕生しました。
ちなみに、この「Telecaster」という名前は、当時テレビの普及が始まっていたことから、「Television(テレビジョン)」の「Tele」に由来しているといわれています。

1952年 Gibson社 Les Paul
ギタリストであり発明家でもあった Les Paul(レス・ポール)も、早くからソリッドボディ・エレキギターの開発に取り組んでいました。
市販はされませんでしたが、1940年ごろにはパイン材のブロックで作られた The Log(ザ・ログ) というモデルをすでに制作しており、この試作機を Gibson社に持ち込んだものの、当時は受け入れられなかったといわれています。Gibson社は老舗メーカーとして伝統的なギター製作を堅実に続けていたため、ソリッドボディ・ギターに対しては慎重な姿勢をとっていたのです。
しかし、競合である Fender社のソリッドボディ・ギターが普及し始めると、Gibson社にもプレッシャーがかかり、1952年についに Les Paulモデルとしてソリッドギターを発売しました。
このギターは、一度は門前払いした Les Paul のアイデアを取り入れると同時に、人気ミュージシャンであった彼の名前を冠することで、シグネチャーモデルとして販売されたのです。

余談〜
Les Paul は2009年にこの世を去りました。
1997年に放送されたアメリカのビール「Coors(クアーズ)」の CM に Les Paul が出演している CM がかっこいいので、みなさんにシェアします。
https://youtu.be/DDxCQ7oJJZ8?si=1bzYtrEd6POV9tUK
ロックンロールの流行
1950年代、エレキギターはさらに普及していきました。
この頃のアメリカでは「ロックンロール」という音楽ジャンルが確立し始めていました。
ロックンロールについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
このロックンロールにおいて、エレキギターは欠かせない存在となりました。
また、それまでリズムバッキングを担うことが多かったギターは、ロックンロールのアーティストたちによってフィーチャーされ、主役級の楽器へと押し上げられていきました。
1954年 Fender Stratocaster
現在でも人気モデルとして知られる Stratocaster(ストラトキャスター)。
このギターは1954年に発売され、初めて「コンター・ボディ」が採用されました。
コンター・ボディとは、演奏時に体へフィットしやすいように施されたボディ加工のことです。
また、「シンクロナイズド・トレモロ・ユニット」が搭載されたのも特筆すべき点でしょう。
シンクロナイズド・トレモロ・ユニットとは、ギターに取り付けられたアームを操作することで音程に揺らぎを加え、ビブラートをかけられるユニットのことです。

1958年 ハムバッカーピックアップの登場
Gibson社の Les Paul には、当初は P-90 と呼ばれるシングルコイルが搭載されていました。しかし、このシングルコイルにはノイズが発生してしまうという欠点があったのです。
このノイズを軽減するべく、Gibson社の従業員であった Seth Lover(セス・ラバー)らによって開発が行われ、最初のハムバッカー・ピックアップが開発されました。
このハムバッカー・ピックアップは、当時特許を出願していたため、裏面には「Patent Applied For」と記載されており、その頭文字をとって「P.A.F」と呼ばれるようになりました。
この「P.A.F」を搭載したギターであるサンバースト・レスポールは1958 〜 1963年の間に発売され、今では語り継がれる名機として、ピックアップ単体でも高値で取引がされています。

ロックミュージシャンとギター
1960年代に入ると、ロックが大きな人気を集め、The Beatles(ビートルズ)や The Rolling Stones(ローリング・ストーンズ)といったバンドの登場により、エレキギターはさらに注目されるようになり、同時に、ミュージシャンたちによるギター表現も大きく広がっていきました。
特に Jimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)は斬新なサウンドメイクで知られ、エレキギターの可能性を大きく切り開いた存在です。彼の革新的なトレモロアームの使い方は、想定している使い方と違うと、設計者であるレオ・フェンダーを怒らせたという逸話も残っています。
エレキギターによる表現はさらなる追求がされていったものの、エレキギター自体の基本構造やサウンドの幅、デザインなどはこの頃からあまり大きな変化はありません。そのためエレキギターは1960年頃に既に基本的な構造が完成されたとされています。
まとめ
以上、今回は初期のエレキギターの歴史についてご紹介しました。
今回は1960年までの Fender と Gibson を中心にご紹介しましたが、同時期から Gretsch社や Rickenbacker社、1960年以降にもIbanez社、70年代後半には Jackson社、80年代にはPRS guitar など、現在に至るまでに様々なギターメーカーが多種多様のエレキギターを作成していきました。
また、エレキギターは同じモデルであっても時代が進むにれて改良が加えられていたり、古いギターだと当時しか使えなかった素材が用いられたりするなど、製造年代によって細部が異なります。この違いは、当然音の違いにも繋がります。そのため、ヴィンテージギターを求める人もいたり、特定の年代のギターを再現した復刻版が販売されることもあるのです。
「一見すると見た目は同じなのに、名前や値段が全然違う「ヴィンテージギターって何?」といったギター好きじゃないとなかなか知らない部分も、歴史を知ることで何となくイメージがついたのではないでしょうか。
このようにギターだけではなく、歴史を知ることで「今」を知ることができます。以下の記事ではドラムの歴史もご紹介しているので是非合わせてご覧ください。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。