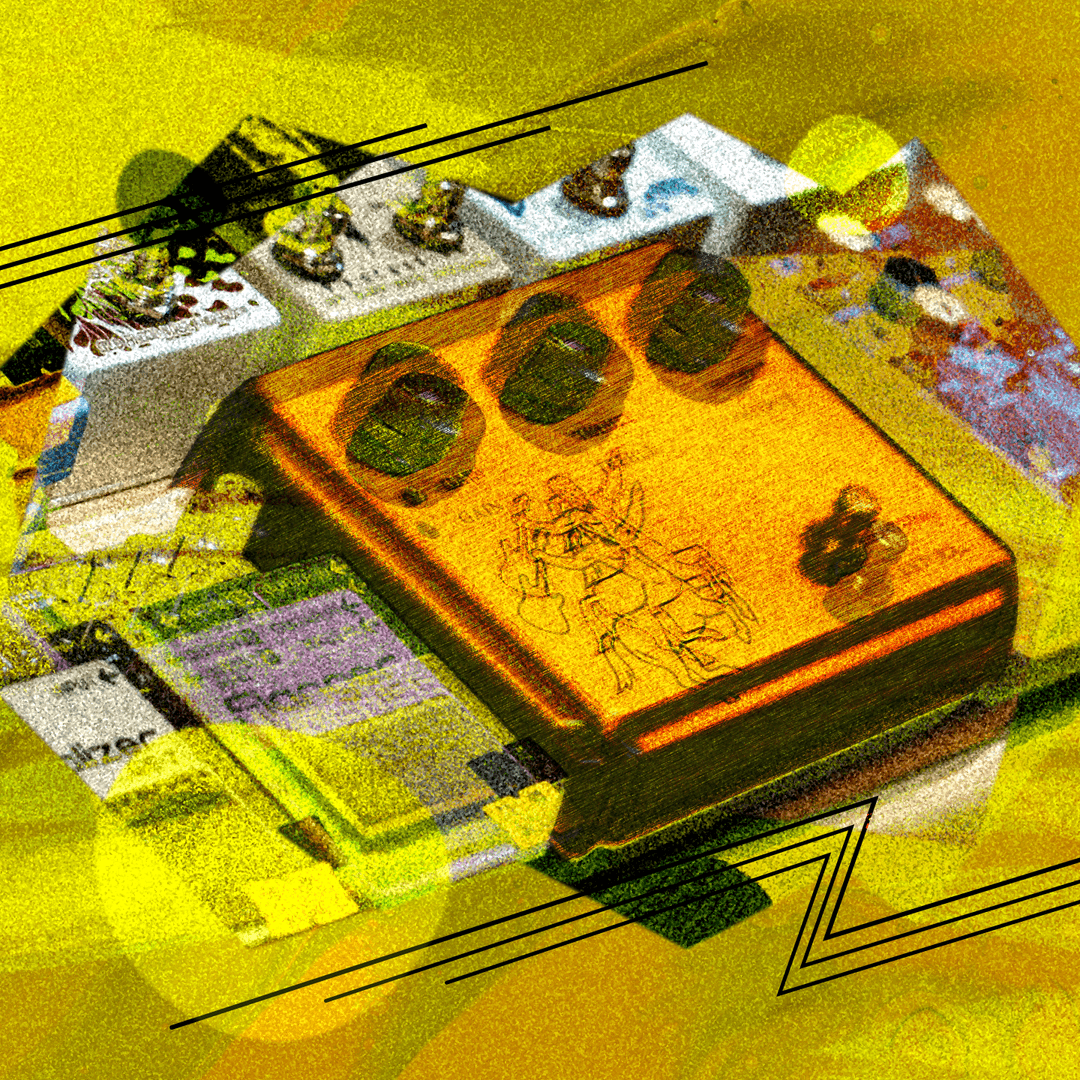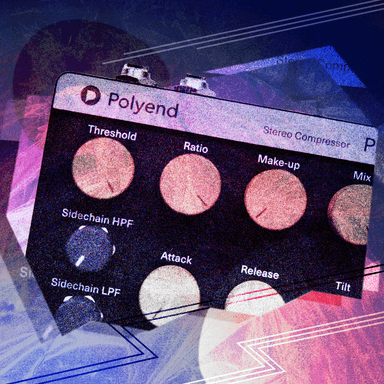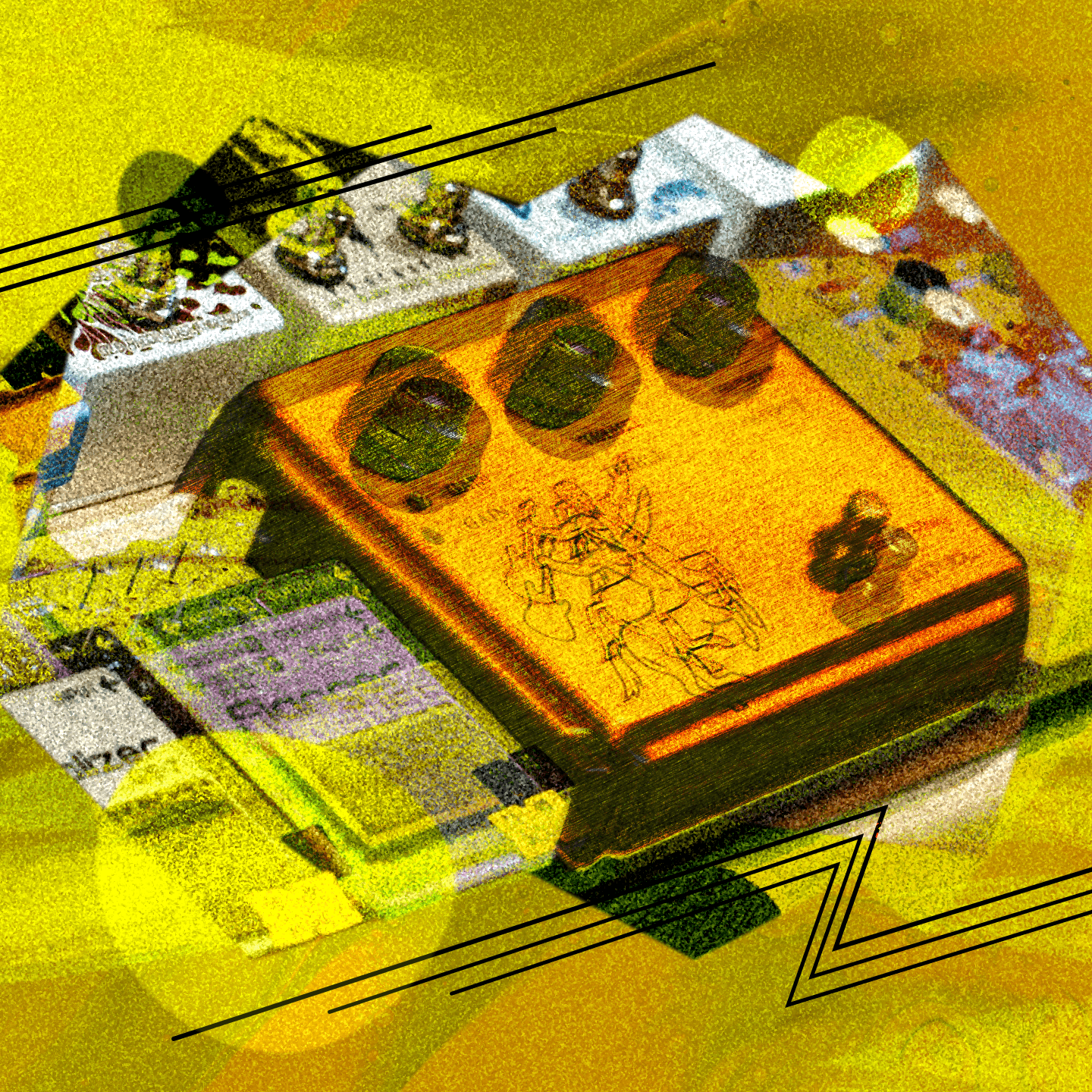

 制作応援キャンペーン開催中!
制作応援キャンペーン開催中!Overdrive / Distortion
Klon Centaur
Klon Centaur は、今回ご紹介する中では、比較的新しいエフェクターです。
このエフェクターは、真空管アンプのボリュームを上げた時に得られるリッチなサウンドをボリュームを下げても再現したい、という製作者 Bill Finnegan(ビル・フィネガン) の想いをきっかけに開発が開始され、1994年から2008年にかけて販売されていました。
ペダルを使用していることが分からないほど自然で、まるで真空管を鳴らしたようなサウンドが得られるこのエフェクターは、販売時から高い人気を誇っていました。しかし、Bill Finnegan(ビル・フィネガン)がハンドメイドで制作していたため供給が追いつかず、当時から中古品が現行品よりも高値で取引される現象が起き、Klon Centaur は生産を終了せざるをえなくなりました。
現在、オリジナル品は約8,000台しか出回っておらず、伝説的なオーバードライブエフェクトとして数十万円〜百万円近くのプレミアム価格で取引されています。
愛用者は John Mayer(ジョン・メイヤー)や Noel Gallagher(ノエル・ギャラガー)などです。
2014年からは、Klon Centaur のサウンドを引き継ぎつつ、価格や製造面で改良された後継機「Klon KTR」が発売されています。
このモデルには「Kindly remember: the ridiculous hype that offends so many is not of my making」(訳:どうか覚えておいてください、人々を不快にさせるこの馬鹿げた誇大広告は私の作ったものではありません)と、Bill Finnegan の想いが刻まれています。
また、この名機のサウンドを再現しようと、Electro-Harmonix Soul Food や Wampler Tumnus など、別メーカーから Centaur をモデルにした機器も数多く発売されており、このような機器は「ケンタウロス系」とも呼ばれ、Centaur のサウンドを引き継いでいます。
その他 Fazertone「THE KLONE」など、 Klon Centaur をモデルとするエフェクトプラグインも存在します。
Ibanez Tube Screamer TS808
Ibanez Tube Screamer TS808 は、1979年に Ibanez社という星野楽器とする日本の楽器メーカーから発売されたコンパクトエフェクターです。
この Tube Screamer の初代機である TS808 は、当時すでに発売されていた BOSS の OD-1 に対抗できるモデルを作ることを目標に開発されました。
TS808 は、単体で強く歪ませるエフェクターというよりも、アンプの歪みを増幅することを目的としたエフェクターで、サウンドの特徴は、まろやかで中音域が太く、原音と歪ませた音が自然にミックスされている点が挙げられます。
著名な愛用者は Stevie Ray Vaughan(スティーヴィー・レイ・ヴォーン)や Lee Ritenour(リー・リトナー)などです。
1970年代後半に登場したこの TS808 は、Ibanez からの復刻版や MAXON OD808 Overdrive など後続機やクローン機も多数発売されており、これらは「TS系」と呼ばれ、現在でもそのサウンドは愛されています。
Tube Screamer のラインナップとして、1981年から1985年に製造された TS-9 もビンテージとして人気があり、市場では数万円で取引されています。
Fuzz
Sola Sound Tone Bender
Sola Sound Tone Bender は、この後にご紹介する、Ram's Head Big Muff Pi 、Dallas Arbiter Fuzz Face と並ぶ、三大ファズエフェクトの名機です。
最も初期のモデルは1965年に Sola Sound 社から発売されました。
この Tone Bender は、イギリスのギタリスト Vic Flick(ヴィック・フリック) が、当時人気のあった Maestro FZ-1 Fuzz-Tone のサステインを長くするよう、エンジニア Gary Stewart Hurst(ゲイリー・スチュワート・ハースト) に依頼したことから開発されたことから始まったとされています。
愛用者はJimmy Page(ジミー・ペイジ) や Jeff Beck(ジェフ・ベック) などで、1960年代のブリティッシュ・ブルース・ロックのサウンドを作る一翼を担いました。
現在は、Tone Bender Mk II をモデルに BOSS と Sola Sound が共同開発した TB-2W が発売されており、往年のサウンドを現代でも体験することができます。
Ram's Head Big Muff Pi
Ram's Head Big Muff Pi は、Electro-Harmonix社が1969年から発売しているファズエフェクター Big Muff の中でも、1973年から1977年頃まで販売されていた2代目モデルです。
Ram's Head Big Muff Pi は、数あるモデルの中でも特に人気が高く、ビンテージエフェクターとして名高い存在です。
サウンドの特徴は、ギターの音を力強く押し出すような、濃厚でサスティーンの長いファズサウンドです。
使用者には、David Gilmour(デヴィッド・ギルモア)や Billy Corgan(ビリー・コーガン)などがいます。また、このエフェクターのプロトタイプ(※1)は Jimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)も愛用していたことで知られています。
Electro-Harmonix社は一度倒産を経験しましたが、現在は Ram's Head Big Muff Pi の復刻版が販売されており、往年のサウンドを現代でも楽しむことができます。
こうした製品群は「ビッグマフ系」と呼ばれ、多くのギタリストに親しまれています。
(※1)改良を前提とした、最初のモデル。
Dallas Arbiter Fuzz Face
Dallas Arbiter Fuzz Face は、Arbiter Electronics Ltd. が1966年に販売を開始したファズエフェクターです。
このエフェクターはマイクの底の円盤部分を基にデザインされており、つまみとロゴが顔になっている見た目も印象的です。ちなみにその製作者である lvor Arbiter(アイヴァー・アービター)は、ビートルズのロゴをデザインした人物としても知られています。
初期モデルは1966年から1967年頃に販売され、その後 Arbiter Electronics Ltd. は別会社と合併。さらに買収などの変遷を経て、Fuzz Face の生産は1975年頃に終了しました。
このエフェクターは、Jimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)が使用したことでその名が世界に広まりました。1970年代には Eric Clapton(エリック・クラプトン)や David Gilmour(デヴィッド・ギルモア)も愛用し、ブルース・ロックのサウンドに大きく貢献しました。
サウンドは、太く厚みのあるファズサウンドで、独特の揺らぎとウォームな中低域が特徴です。
現在では Jimi Hendrix が使用していた Fuzz Face を再現した JIM DUNLOP JH-F1 などの製品があり、こうした製品は「ファズフェイス系」と呼ばれています。
その他
Shin-Ei Univibe
日本の会社であるHoney(Shin-ei / シンエイ)によって1960年代に発売されたモジュレーション系のエフェクターです。
開発をしたのはエンジニアである三枝文夫氏。
最初の開発のきっかけは、当時モスクワ放送を聞いた際に、その音色の変化を音楽に活かせないかと思ったと明かしています。
この Shin-Ei Univibe のサウンドはコーラスやビブラート、トレモロなどを組み合わせたようなサウンドを作るエフェクターですが、実際にはより複雑で揺らぎのある音色変化を生み出すのが特徴です。
Jimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)も愛用しており、1969年の伝説的なロックフェス「ウッドストック・フェスティバル」出演時にも使用していたことは、ギターキッズの間でも有名なエピソードです。
現在では、60年代の Univibe を再現したクローン機器として Vibe 2 CHORUS / VIBRATO なども発売されており、往年のサウンドを現代でも楽しむことができます。こうした製品は「ユニバイブ系」と呼ばれ、多くのギタリストに親しまれています。
まとめ
以上、今回は有名なヴィンテージギターエフェクターをご紹介しました。
今回はクローン機や復刻版についてもご紹介しましたが、そのサウンドは人によっては物足りなかったり、別ものと感じる方も少ないようです。
そもそも、ヴィンテージもののエフェクターは個体差が顕著なものもあり、なかには同じモデルでも理想の個体と出会えるまで売り買いを繰り返す方もいます。なかなか奥が深い世界ですね。
また、愛用者も豪華な顔ぶれで、このような名機は様々な名曲の一部を担っており、音楽の歴史にも重要な役割を果たしています。
まだまだ紹介しきれなかったものはたくさんありますが、重要なサウンドを知っておくことで、自分の作りたい曲にも活かせるでしょう。
是非ご参考にしてみてください。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。