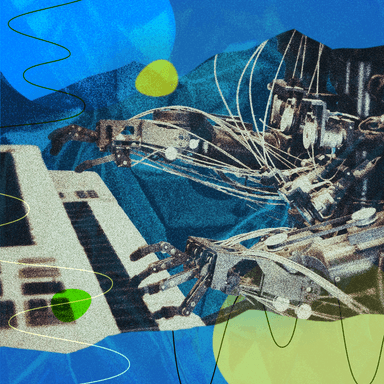劇場版『チェンソーマン レゼ編』エンディング・テーマとして書き下ろされた楽曲
「JANE DOE」は、2025年9月公開の映画・劇場版『チェンソーマン レゼ編』のエンディング・テーマとして米津玄師が書き下ろした楽曲です。
米津は今回の劇場版のために2曲の楽曲制作依頼を受けており、もう一曲は映画の主題歌である「IRIS OUT」で、この2曲は両A面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」として、9月24日に発売されました。
2022年に放送されたTVアニメ版『チェンソーマン』のオープニング・テーマ「KICK BACK」も米津が手がけていたため、アニメ版・劇場版の両方の楽曲を担当する形となりました。
「JANE DOE」は映画のラストを飾る楽曲で、映画の内容を知らなくても世界観が素敵で引き込まれてしまいます。どんな物語の内容が米津玄師の世界観を通して、楽曲に反映されているのかを見ていきましょう。
劇場版『チェンソーマン レゼ編』ってどんな話?
この映画の主人公はチェンソーマンの「デンジ」と少女「レゼ」。デンジは父親の借金の返済をするためデビルハンターとして働く少年です。一方レゼはカフェ「二道」で働いているのですが、デンジは彼の上司であるマキマに想いを寄せながらも、レゼに恋をします。
普通の日常を望んでいたデンジとレゼとの一夏の恋が描かれますが、レゼには隠された「秘密」があり....
公開後のキャッチ・コピーは「誰も知らない、少女の心」。レゼの生い立ちや運命が絡み合う中で、映画では一筋縄ではいかない複雑な2人の非恋の物語が描かれています。
インスパイアされた楽曲 Björk「I've Seen It All」
米津玄師はこの劇中歌を描き始める時にイメージにあったのは、2000年に公開された Björk (ビョーク)主演の映画『Dancer in the Dark(ダンサー・イン・ザ・ダーク)』の劇中歌である「I've Seen It All」だったとのこと。
この曲は Björk が演じる Selma(セルマ)と、セルマに恋心を寄せる Jeff(ジェフ)のデュエット曲です。
Selma は、遺伝性の病気によって徐々に視力を失っていく中でも、息子のために懸命に働く女性。彼女の事情を知りながらも、その苦しみの深さまでは理解しきれず、ただ純粋に彼女を想う Jeff。
Selma が「もう十分見てきた」と達観して歌う一方で、Jeff は「まだ見る価値があるものがある」と歌っており、交わることのない男女を表すデュエットの構図は、米津がインスパイアを受けたというのも納得です。
宇多田ヒカルへのボーカル依頼
『チェンソーマン レゼ編』の中心人物はレゼという少女であるため、米津玄師は楽曲制作の初期段階から、ボーカルは自分一人で歌うのではなく、女性の声を取り入れることを視野に入れていたのだそう。
A メロの制作途中で、宇多田ヒカルの声がイメージに合うと感じ、その想いのもと、米津から宇多田へ正式なオファーが届き、快諾。夢のデュエットが実現しました。
宇多田はロンドン在住のため、ボーカル録音のデータのやり取りはすべてオンラインで完結したのだとか。まさに現代的な制作スタイルと言えるでしょう。
また、米津はボーカルを依頼する際、複雑な事情を抱える少女と、それを理解しきれない少年の掛け合いをイメージしており、このイメージが宇多田に伝えた唯一の要望だったといいます。
宇多田ヒカルの憂いを帯びた声と深い表現力が、複雑な背景を持つ物語を表現した切ない歌詞の世界観にさらに奥行きを与えています。
サビ前のかすかな吐息さえもアレンジの一つとしてリスナーを惹きつけ、サビをより印象的に演出しています。
楽曲の特徴
メロディー
Aメロのメロディーは3拍子を強く感じるリズム。Bメロでは Aメロよりも細かい符割になり跳ねたリズムも取り入れています。サビではバックで入るキックとスネアも相まって大きな2拍子を感じさせる構成になっています。
音程も見てみましょう。
短調で紡がれていくメロディーはメランコリックでどこか翳りを感じさせます。
1番Bメロの「指に」の「に」の音程に注目です。本来であればミで歌われるところを、半音上のファを一瞬だけ経由しており、そのニュアンスがとてもかっこいいです。
サビでは10度以上離れた跳躍の音程で始まり、A、Bメロとはまた違う表情を感じさせています。
「足跡を」の音程は、キー以外の音も取り入れられることによって、より切なさが際立っています。
印象的な「余白」
楽曲全体として余白(ブレイク)の使い方が印象的です。
1番のサビに入る前には、2小節と長めのブレイクが入ります。宇多田の吐息がその間に入ることでリスナーをぐっと惹きつけられ、次にくるサビのインパクトを高めています。
サビはストリングスが入り壮大な雰囲気で始まりますが、一回しめの「歩く」という歌詞の終わりにシンセサイザーだけが残されたり、サビ終わりの「会いにきて」というフレーズの部分でまたブレイクが入ります。ブレイクを上手く利用して楽曲に緩急を生み、ドラマチックさを演出しています。
また、厳密にはブレイクではないですが、2番Bメロの2人の掛け合いの最後は米津一人で歌われ、うしろの伴奏もピアノとピチカートのみになり、ポツンと一人残された印象を感じさせます。
2人による掛け合い
特に2番のBメロでは2人の掛け合いがあり、宇多田と米津の歌い方の違いにも注目です。
米津はまっすぐ気持ちを歌っているような印象がある一方で、宇多田はどこか達観したような落ち着いたように感じさせる歌い方。
「宇多田ヒカルへのボーカル依頼」の章で触れた要望に沿って、男女が違う方向を向いていることが感じられます。
歌詞
映画の内容とリンクする歌詞によって、ファンからは考察が止みません。
特にサビの歌詞は、米津玄師がレゼというキャラクターからイメージした光景を強く反映させていると明かしています。
タイトルの「JANE DOE」は、身元不明の女性を指す仮名として使われる言葉であり、レゼの生い立ちとも重なります。
劇中でレゼがロシア語で歌うシーンがあり、その歌詞の中に「ジェーン」という人物が出てきていますが、米津自身は制作中は意図していたわけではなかったと語っています。無意識下でリンクしていたものもあるというのが興味深いですね。
制作陣にも注目!
編曲には Yaffle も参加
Yaffle は日本の音楽プロデューサーで、これまでに米津の作品だけでなく、藤井風や SIRUP などの人気のアーティストを手掛けています。
また、劇伴作家としての顔を持ち、過去には『映画 えんとつ町のプペル』や『ナラタージュ』などの音楽制作も担当。
エンジニアは小森雅仁・齊藤 裕也
レコーディングは小森雅仁と齊藤裕也が担当。
小森は前述の「KICK BACK」をはじめとした米津の作品のほか、宇多田の『Fantoome』や『BADモード』などのアルバムにも携わってきた人物です。また、本楽曲のミックスも担当しています。
齊藤 裕也もまたこれまでに宇多田ヒカル、大原櫻子など数々のアーティストの楽曲制作に関わってきた第一線で活躍する人物です。
まとめ
筆者は米津玄師と宇多田ヒカルがコラボ曲を発表したと知り合いから聞いた時に、両者に似た系統のイメージがなかったため「どんな曲になっているんだろう?」とワクワクしながら聴きました。日本が誇るアーティスト2組によるコラボは胸が踊りますね。
宇多田ヒカルは自身のほとんどの曲を作詞作曲しているため、歌唱のみで誰かの作品に参加することはかなり珍しいのだとか。
カバーはこれまでには出しているとは思いますが、他者の歌詞を歌った宇多田ヒカルの歌声も、この楽曲ならではの魅力でしょう。
また、この豪華コラボにおいて欠かせなかったのは、『チェンソーマン レゼ編』。この楽曲の Youtube のコメント欄を見ると、映画を振り返って余韻に浸っている人や、映画の内容を踏まえて楽曲やMVを考察している人、映画で流れて来た時の感想を伝えている人などがいて、みなさん様々な楽曲の楽しみ方をしていました。
そんな Youtube の再生回数は公開から4週間ほどで2000万再生もされています。
そのような様子から、映画のラストを彩り、観客に没入感だけではなく余韻を持たせていることが分かります。この楽曲が映画をさらに盛り上げる役割を担当しており、エンディング・テーマの制作は、改めて重要且つ大きな仕事なのだと思いました。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。