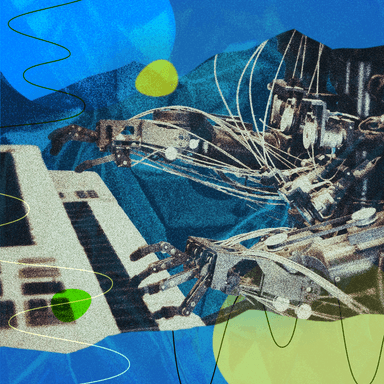コード初心者の方は、この記事と合わせて以下の記事も一緒にご覧いただくことで、より理解が深まると思います。
J-POP はコードが複雑なものが多い?
現代の洋楽(特にヒットチャートの上位に並ぶような曲)では、比較的コード進行がシンプルな楽曲が多い傾向にあります。一方で、J-POP はコードの展開が多く、使用されているコード進行が複雑な曲が多いと言われています。
実際に近年のヒット曲を比較してみると、その傾向が見えてくるでしょう。
例えば、2024年の Billboard Global チャートで1位を獲得した Teddy Swims(テディ・スウィムズ) の『Lose Control』では、Aメロ(Verse)もサビ(Chorus)も、基本的には F#m → A → D → Db7 という進行の繰り返しで構成されています。
一方、同時期に日本で大ヒットした tuki. の『晩餐歌』を見てみると、Aメロ・Bメロ・サビでコード進行がそれぞれ異なります。
他にも、King Gnu や Official髭男dism など近年人気なアーティストの曲の、コード進行による構成の緻密さや展開の多さは、J-POP の特徴の一つだと言えるでしょう。
とはいえ、J-POP における複雑なコードは、元々は洋楽からの影響がベースになっています。そこに、日本独自の音楽感覚や、日本語が持つ言語的特性などが重なり合うことで、現在のコード進行のスタイルが形成されてきたと考えられます。
※ あくまで「一般的な傾向」としてご理解いただければと思います。
複雑に聞こえる理由3選
では、コード進行が複雑に聞こえる要因は何でしょうか?主に考えられることとして、以下の3つが挙げられるでしょう。
ノンダイアトニックコードの使用
ノンダイアトニックコードとは、「そのキー(調)に属さないコード」のことです。
本来、それぞれのキー(調)には、主に使用されるコードが決まっています。それらをダイアトニックコードと呼び、Cメジャーキーの場合、C・Dm・Em・F・G・Am・Bm7(♭5) といったコードがこれにあたります。
ノンダイアトニックコードは、これらダイアトニックコード以外のコード、つまり「他のキーから一時的に借りてきたコード」や、「スケール外の音を含むコード」を指します。
これらをうまく使うことで、意外性のある響きや、ドラマチックな展開を演出することができます。
分数コード
分数コードとは、ベース音(一番低い音)がそのコードのルート以外の音になっているコードのことです。
(コード名)/ (ベース音)、もしくは (コード名)on (ベース音)で表されます。
通常、コードのベース音はそのコードのルートになりますが、ベース音をルート以外にすることで、ベースラインを滑らかにしたり、コードの響きに広がりを持たすことができます。
転調
転調とは、曲の途中でキー(調)を変更することを言います。
先ほどご紹介したノンダイアトニックコードも、使い方によっては、一時的な転調とも言えるものもあるでしょう。
分析をするまえに・・・
鉄則:ディグリーネームで考える
コード進行を分析したり、コードを自分の技の一つとして取り入れる場合の鉄則として、必ずディグリーネームで考えましょう。
そうすることで、キーが違う曲でも同じ機能のコードを見つけやすくなったり、自分の楽曲に取り入れやすくなります。
前提:ダイアトニックコードを把握
ダイアトニックコードは、その調で使用されるコード群のことです。
メジャーキーの場合、ディグリーネームで考えた場合のダイアトニックコードは以下になります。
I IIm IIIm IV V VIm VIIm7(-5)
ディグリーネームとダイアトニックコードについては、冒頭でもご紹介した以下の記事で詳しく解説しています。「まだよく分からない」という方は、先にこちらを読んでいただくことで、次章の理解が深まります。
次章では、実際の曲を例に、上記のようなダイアトニックコード以外、つまりノンダイアトニックコードが使われているコードワークを考えてみたいと思います。
実際の曲からコードワーク例をご紹介
<題材>Mrs. GREEN APPLE『クスシキ』
KEY:Eメジャー
※この章のコード進行は、耳コピ・分析に基づいた予測であり、実際の楽曲制作者の意図や公式譜面とは異なる場合があります。
・ IV → IVm
原曲キー:C#m → E/G# → A → Am → E
デイグリーネーム:VIm → I/III → IV → IVm → I
ノンダイアトニックコード:IVm
10〜13小節目の Aメロの一回し目のコードです。メジャーキーと考えた場合、VIm はノンダイアトニックコードですが、 IV → IVm は、定番の動きです。
この進行は、どこか切ない印象を与えます。
・bVI→bVII
原曲キー:E → G# → A → C → D
デイグリーネーム:I → III → IV → bVI → bVII
ノンダイアトニックコード:III、bVI、 bVII
これは、17小節目、Aメロの2回し目のコード進行です。
この bVI → bVII という動きも定番であり、同主調からの借用と考えられます。
明るく、次の展開がわくわくするような印象です。
・半音ずつ下がる
原曲キー:C#m → Caug → E/B → A#dim
デイグリーネーム: VIm → bVIaug → I/V → #IVdim
ノンダイアトニックコード:bVIaug、#IVdim
Aメロ2回し目の、18小節、19小節に出てくるコード進行です。
オーグメントコード(aug)や、ディミニッシュコード(dim)、分数コードを使用して、ルートが半音ずつ下がるようなコード進行になっています。
・半音ずつ上がる
原曲キー:A → A#dim → B
ディグリーネーム:IV → #IVdim → V
ノンダイアトニックコード:#IVdim
サビの手前のコード進行です。
IV と V の間にディミニッシュコードを挟むことで、ベースラインが半音ずつ上がる進行になっています。
・III
原曲キー:C#m → G# → A → G#
ディグリーネーム:VIm → III → IV → III
ノンダイアトニックコード: III
2番Aメロの始めのコード進行です。
本来 IIIm となるところを III とすることで、哀愁のあるコード進行になっています。
この III は、ヒット曲に多く含まれており、多くの人に愛されている響きです。
・転調
ラストのサビで、半音上のキーに転調しています。
これも定番の転調の仕方と言えるでしょう。
まとめ
今回は、J-POP のヒット曲に見られる複雑なコード進行の一例を見てみました。最初から理論を完璧に理解しようとする必要はありません。まずは「響きの印象」を体で覚えることをおすすめします。
例えば、IV → IVm はちょっと切なくなるような響き、♭VI → ♭VII は明るく開ける感じで、次の展開へのワクワク感を生む…など。コードの雰囲気を掴むことで、別の曲で同じコード進行が出てきたときに、「あっ、あの曲にもあったやつだ!」と気づけるようになったり、オリジナルを作っている時も「ここにあのコードを入れたら合うかも!」など、自分の作曲やアレンジにも活かせるようになっていくと思います。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。