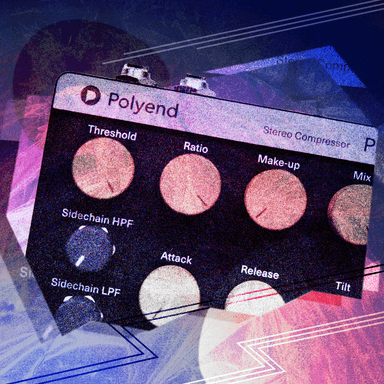制作応援キャンペーン開催中!
制作応援キャンペーン開催中!キーとは?
キーとは、楽曲を構成する音のグループのようなものです。1つのキーは、7つの音から構成されています。
私たちが聞き慣れているポップスは、何かしらのキーに当てはまります。
つまり、数多くの楽曲はそれぞれ7つの音の組み合わせで作られているということです。
「キーを知らないと作曲できないの...?」と不安に思った方も、ご安心ください。
たとえ音楽理論を知らない人が作曲をしたとしても、私たちがアウトプットするものは、普段インプットしているものに基づいて行われます。
私たちは普段からキーに基づいた楽曲を耳にしているため、感覚に頼って作曲をしても大抵の場合は嫌でも何かしらのキーに当てはまるのです。
キーには明るい響きをもつ「メジャーキー」が12種類と、暗い響きをもつ「マイナーキー」が12種類で、合計24種類あります。
キーはどのように構成される?
先ほど、キーは7つの音から構成されているとお伝えしました。
では、その7つの音はどのように決まるのでしょうか?
キーには必ず「主音(しゅおん)」と呼ばれる、中心となる音があります。
この主音を出発点にして、「ある規則」に従って音を並べていくことで、そのキーの構成音が決まります。
この「ある規則」とは、主音からどのような音程(音の間隔)で音を積み重ねるか、というルールのことです。
この音の並び方の違いによって、「メジャースケール」と「マイナースケール」という2つのスケールが生まれます。
このスケール(音階)= キーの構成音となります。
スケールについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になるでしょう。
ちなみに、ド(C)からオクターブ上のドまでには、半音で12個の音があります。
それぞれの音を主音にした「メジャースケール」と「マイナースケール」があるため、キーの種類は全部で24個(12音 × 2スケール)あるということになります。
メジャーキー一覧
メジャーキーは、メジャースケールで構成されています。
メジャースケールは主音を基準にし、音を「全全半全全全半」(※)という規則に従って、音を並べたものです。
(※)全=全音、半=半音

マイナーキー一覧
マイナーキーは、マイナースケールで構成されています。
マイナースケールは主音を基準にし、音を「全半全全半全全」という規則に従って、音を並べたものです。

メジャーキーとマイナーキーの関係性
先ほどのキー一覧の画像を見てお気づきの方もいるかもしれませんが、メジャーキーとマイナーキーには、構成音がまったく同じペアが存在します。
この関係は「平行調(へいこうちょう)」と呼ばれます。
例えば、 Cメジャーと Aマイナーを見てみると、順番は違いますが、使われている音は同じことが分かります。
使われている音は同じでも、曲の雰囲気や中心に感じられる音の違いによってキーが分けられているのです。
そのため、構成音だけで考えた場合、キーのパターンは全部で12通りしかありません。
構成音が同じであっても、楽曲が明るく感じられる場合は Cメジャー、暗く切ない印象を受ける場合は Aマイナーとなります。
また、曲の最後の音など「終わった」と感じる音が C であれば Cメジャー、A であれば Aマイナーというように、音からもキーを判断することができます。
楽曲のキーの調べ方
楽曲の最後の音から判断
私たちが曲を聴いていて、曲が「終わった」と感じる場合、大抵の場合はそのキーの主音が使われています。そのため、楽曲の最後の音には主音が使われている場合が多いです。
ただし、必ずしも最後の音=主音というわけではないため、注意しましょう。
メロディーの構成音から判断
メロディーをまずは耳コピしてみて、その使われている音から判断する方法です。
メロディーの構成音は12パターンあります。例えば、「ドレミファソラシド」の7つの音が使われていた場合、それは Cメジャーキーか Amキーのどちらかになります。
番外編:転調について
「転調」という言葉を聞いて、なんとなくイメージが湧く方も多いのではないでしょうか。
転調とは、楽曲の途中から、もしくは一部が別のキーに変わることを指します。
例えば、最後のサビでキーを上げることで盛り上げたり、楽曲の途中でアクセントを加えたり、世界観をガラッと変えたりする際によく使われます。
ポップスからクラシックまで、さまざまなジャンルで使われるテクニックです。
番外編:カラオケのキーについて
カラオケのキー設定は、自分が歌いやすい音程に合わせて、楽曲全体のキーを半音ずつ上下に調整できる、キーの概念を応用したシステムです。
すべての音が半音単位で移動するため、メロディや楽曲の雰囲気を変えることなく、自分の声に合った高さで気持ちよく歌うことができます。
まとめ
以上、今回は「キー」についてご紹介しました。
一見すると複雑に感じられる「キー」という概念ですが、じつは音楽理論のすべての土台となる、とても大切な考え方です。
最初は難しく思えるかもしれませんが、スケールやダイアトニックコードなどとあわせて少しずつ理解を深めていけば、きっと自然に身についていくはずです。
また、キーが何となくわかった!という方は、コード理論にも挑戦してみてはいかがでしょうか。
以下の記事では、コード進行の組み立て方を解説しています。ぜひご参考にしてみてください。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。